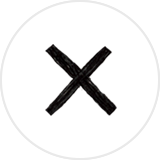2025年3月17日
こんにちは、シナプス代表の竹内です。生成AIがはやりだして2、3年でしょうか。2022年にOpenAI社が公開した「ChatGPT」がきっかけですが、いまやあらゆるサービスへの応用が進んで、「最新AI搭載!」みたいな家電製品のキャッチコピーも珍しくありません。どこがAI?というサービスもあったりしますが。
ChatGPTが登場してしばらくは文字のみでしたが、あっという間に画像・音楽・動画制作や、プレゼン資料の作成まで、広範囲にわたってAIが活用されています。この流れは第4次AIブームと言うらしく、過去の第3次までのブームは定着せずに終結を迎えたようです。ただそれらのブームでの多くの知見の蓄積が、今の第4次の基礎となっています。
ところでAI、さっぱり分かりません!AIの開発者も仕組み・プログラムは作れるものの、AIがなぜその回答を出すのか分かっていない、とも聞きます。ちゃんとAIを分かりたいと思い、「意味がわかるAI入門」という本を購入しました。買ったんですが、もっと事前にちゃんと調べればよかった…。この本の内容は、AIの意味が分かるように解説したものではなく、AIは意味が分かっているか?を論究している本でした。でもせっかく買ったので読んでみました。
どんな本かというと、AIは言葉の意味を理解しているのか、そして「意味を理解する」とは何を指すのかということを解説しています。前半は第1次から第3次までのAIブームの歴史を振り返り、後半では「真理条件意味論」と「分布意味論」という観点から、AIが言葉の意味を理解しているか?について考えていきます。が、すっげー難解!専門家以外でこれ分かる人がいるのか?!と言いたいくらい難解です。
ただ理解度10%未満でも興味深かったのが、チューリングテストとチューターテストです。チューリングテストとは、1950年に数学者アラン・チューリングが提案した、「機械(コンピュータ)が知能を持っているとみなせるかどうか」を判断するためのテストです。それはまず人間の審査員がコンピュータと人間の両方とテキストチャットなどを通じて会話を行います。でも審査員はどちらが人間でどちらがコンピュータかを知らない。審査員がコンピュータを人間と誤認する確率が高ければ、そのコンピュータは「知的である」とみなすというものです。でも、ですね。人をだませたと言っても、それでコンピュータが知能を持っている!って、なんか釈然としません。では学習の度合いが少ない子どもは知能を持っていないといえるのか?など。
ということもあってか、チューリングテストの改良版として提案されたのがチューターテスト(Tutor Test)で、AIの知能をより厳密に評価するためのテストです。単に人間らしい会話ができるかどうかではなく、AIが人間に「教育」できるかを基準にしています。基本的な仕組みはAIが教師(チューター)として機能し、人間の学習者に対して何らかのトピックを教える。学習者は、AIからの指導を受けた後にテストを受け、その理解度を測る。AIの教え方が効果的であり、学習者が適切に知識を習得できれば、AIは「知的である」とみなされる、というもの。ただこれも、ですね…。教え方がうまいからきっと意味を理解しているはずだ、知的とみなそうって、ちょっとやっぱり釈然としません。逆にこの2つのテストの存在が、AIは意味を理解しているか?AIは知性を持っているか?の議論の難しさを象徴している気がしました。
ちょっと前に、岸田元首相のフェイク動画が話題になりました。AIがさらに進化して、画面越しに実物にも思える架空の人と、スムーズなコミュニケーションができるようになります。リアルには存在しない、2次元の嫁の高度版の実現もすぐです。そうなったときに、人は心の底から満足できるでしょうか?満足できそうもない気がします。結局知性・知能とは、言葉や情報のアウトプットだけで判断されるものではなく、相手の存在全体を受け入れて、人が人を感じるものに紐づくのかな?とも思ったりします。と、ここまでがんばって、次に「意味がわかるAI入門」を再度開くのは遠い先になりそうです。
 〒890-0053
〒890-0053 099-813-8690
099-813-8690  https://corp.synapse.jp
https://corp.synapse.jp