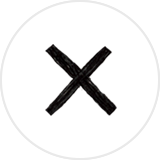2025年9月3日
こんにちは、シナプスの竹内です。
ここでは到底言えない悩みがあります。深刻ではありますが、別にその悩みに押し潰される気はしないし、夜もぐっすり眠れています。ときたま、ねこがエサの催促で大きめの声で鳴いたり、生存確認なのか匂いを嗅ぎに来たりで、安眠を妨げられますが。
世の中、いろんな大事件があります。そしてメディア・マスコミはそういう大事件を報道し、事実のほか、もっともらしい原因や背景、社会への影響などを説明してくれます。大事件の最たるもののひとつは戦争だろうと思いますが、これは報道の他に、教科書などでも知り得て、戦争が起こった理由や、両者の言い分なども分かります。でも最近「対決!日本史6 アジア・太平洋戦争篇」を読んで、うすうす感じていただけのことが、けっこう明確になりました。メディアがもっともらしく、それらしく解説することは、違うのではないか?と。
ちょっと脱線しますが「対決!日本史6 アジア・太平洋戦争篇」は、目からウロコな話が盛り沢山です。例えば旧・厚生省(現在の厚生労働省)は、国民の保健・福祉の増進を目的として設置されたわけではなく、頑健な軍人をつくるために陸軍の主導で昭和13年につくられたそうです。ぜんぜんイメージが違った…。
話は戻りますが、うすうす感じていたこととは「太平洋戦争って、当時の陸軍・海軍の一部の幹部の人間関係や軋轢、世間体という極めて個人的な、そして低レベルなことに起因しているのでは?」というものです。それは大した根拠があるものではなく、タイトルも覚えていない本とか映画とかからの漠然とした印象でしたが、「対決!日本史6 アジア・太平洋戦争篇」には明確に書かれていました。太平洋戦争につながっていく日中戦争、その発端の盧溝橋事件や満州事変など、それらの主要なターニングポイントに陸軍軍人が関わっています。そして彼らの個人的な動機が中心になって、日本は数々の判断ミスを重ねていきます。この本を読んでユネスコ憲章の有名な前文「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。」は、決して理想を書いたものではなく、本質だったんだと思いました。
そして何よりたちが悪いのは、そういった日本をミスリードした人たちの多くが極めて優秀で、大局観(ただし自己陶酔的な大局観)を持ち、そして確信犯だということです。「自分は絞首刑になるだろう」と分かりながらも、やり続ける。こういった人を止める術は思いつきません。「対決!日本史6 アジア・太平洋戦争篇」では、そういった人の欠陥は、民衆の苦しみを想像する力が欠如していることだとありました。本人一人の絞首刑ならまだしも、多くの人々を想像を絶する苦難に巻き込んでいく。怖いのは、これは80年前の話で済まないところです。当時は日露戦争から30年以上経っていて、軍人は戦争体験をしていない人がほとんどだったそうです。なので戦いのリアリティがない、苦しみの実感がない。もちろん国民にも戦争のリアリティはなく、威勢のいい話ばかりする。これって今の、令和の状況と同じです。まあ現代の自衛官がそんな安易に戦争を捉えているような実感はありませんが、実際はどうでしょう。そして国民自身や、国民が選んだ政治家はどうでしょうか。
そしてもう一つ思うのは、これは軍人や政治家、戦争などに限った話ではないかもな、というものです。もしかしたらもっと身近な、会社の中でもあるかも…と。現場を知らずに、社員を知らずに、お客様やお取引先の実状を知らずに、そういった生の感覚を持たない、現場現実から遠く離れたところで、理想論もっといえば空理空論を振りかざしていないか。もしくは分かったふうに勘違いをして、社員に明らかに無駄な消耗を強いていないか。次元は違っても怖いことです。
ただそんな状況でも時間は進み、経営環境は変わり続けます。前に進まないわけにはいきません。悩みながらも、やるしかないですね。
 〒890-0053
〒890-0053 099-813-8690
099-813-8690  https://corp.synapse.jp
https://corp.synapse.jp