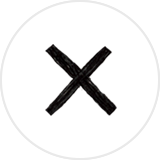2025年7月11日
世界中の皆さんおはようございますこんにちはこんばんは、企画課営業課の福山と申します。
前回、前々回に続いて今回も鹿児島市内の方向けな記事になってしまい申し訳ありません。今回は鹿児島市の中心を流れる二級河川「甲突川」を取り上げます。
いきなりですが、この川、川筋がおかしくないですか?扇状地や平地を流れる川の流れは、普通は「蛇行」するんですが、甲突川の伊敷~新照院区間の川筋を見てみると、自然の摂理では再現出来なさそうなほどに一直線なんです。こちらをご覧ください。
どうですか? 真っ直ぐ過ぎませんか? これって絶対に人為的に川筋を矯正したと思っているんです。もしそうだとすると、その記録や書物がどこかに残っていると思いまして色々と探してみたのですが、どこにもその記録が残っていません。
※ちなみに、甲突川の新照院より下流については、江戸時代初期に大規模な城下町造成計画の一環として流れを変えられたのは有名なお話ですよね。
書物などに記録が残っていないので普通なら諦めるところですが、ちょっと違うアプローチで痕跡を探してみました。
鹿児島神社のご由緒
私は以前、鹿児島県内の神社を調べていた時期がありまして、その時に草牟田に鎮座する「鹿児島神社」について調べたことがあるんですが、その時にこの神社のご由緒に確か甲突川の事が書かれていた事を思い出しまして、改めて調べてみたら、書いてました。
当社の別名を宇治瀬神社と申し上げ、土地では「宇治瀬様」を薩摩弁で「ウッテサァ」と呼んで親しまれて参りました。宇治瀬とは、当社鎮座の故地、錦江湾の神瀬の小島にかかる瀬のいと早く渦巻く様とも、また、以前は当社下を流れていたという甲突川のその早瀬の逆巻く様とも言われております。
ほら、やっぱり。
甲突川はかつて別の姿をしてたんだ! じゃあどこをどんな感じで流れてたんだろう? 気になりますよね。さらに違うアプローチで調べてみました。
町内会の名前
町内会の名前には、今では使われなくなった古来の地名が残っていたりします。
実は鹿児島市が、市内の町内会の情報を掲載したマップを公開してくれているので、このエリアの町内会の名前を調べてみますと、気になる名前が見つかりました。
それは…
- 小野中福良町内会
- 下伊敷中福良町内会
の二つです。
何故かと言いますと、この中福良という地名は川や海と非常に縁が深く、この地名が付いている土地はかつて近くに川が流れていた可能性があります。
なので二つの町内会は、現在はいずれも甲突川とは接していませんが、かつてはその地に川が流れていたと考える事が出来ます。
さらに、小野中福良町内会の場所を古地図で見てみると、ここだけぐにゃっと曲がった変な地形・道があることが分かりますし、この形は現在も道路として残っています。

これって、甲突川の川筋の跡なんじゃね?
ここと下伊敷中福良町内会を繋いで、その先のある鹿児島神社の前を繋いだら、かつての川筋が見えてくるんじゃね?
…ということで、繋いでみました。
かつての甲突川はこんな感じ?
これらの情報を基に、私なりにかつての甲突川の姿を推測してみました。こちらです。
青色の線が私の予想するかつての川筋で、赤色の線は江戸初期に工事がされる前の流れです。
※それとついでに境川の流れも水色で書いてあります。
もちろん、時代によって違う姿をしていた可能性がありますし、そんな単純な話では無いとも思いますが、いい線いってるんじゃないかなぁ… と。
まとめ
ということで、自分なりにかつての甲突川を再現してみましたが、もちろん完成度はまだ低いと思っています。電柱・電信柱の名前にもかつての地名が残っていたりするので、それも調べてみたらもっと正確な川筋が見えてくるかも知れませんね。
 〒890-0053
〒890-0053 099-813-8690
099-813-8690  https://corp.synapse.jp
https://corp.synapse.jp